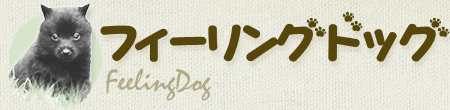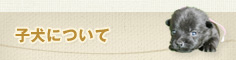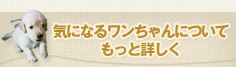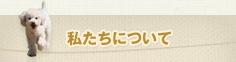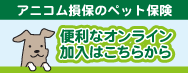2016年10月05日
犬の育て方は子育てとほぼ一緒★
犬の育て方は子育てとほぼ一緒★
子供に「して良いこと・悪いこと」を教えるのは、親の役目ですよね。犬を家族にするということは、人間の子供の親になったと同じこと。社会の一員として暮らしていく上で大事なことを教え、明るい思いやりのある子にする育て方は、人間の子育てと同じなのでしょうか?違うのでしょうか?実は、共通するところがたくさんあるんですよ。
私は良くトレーニングに来られたオーナーさんに「犬は子供と一緒!」とよく言います。それは私自身が現在ママだからわかることなのかもしれません。独身の時には全く気づきもしませんでしたが、自分の子供といぬのトレーニングは似ていることが多いなぁ~と感じて犬のしつけ同様にうちの子供たちを育てました。
まず、犬も子供も≪他人に迷惑をかけない≫というのを大切にしています。犬の場合は人を噛まない、無駄吠えしない、むやみに飛びつかない、他犬に慣れる。がどんなわんちゃんでもとっても大切なこと。
人の子の場合は友達に手を出さない、挨拶をきちんとする、危ない行動をとらない、他人がいるところで騒がせない、が大切ですよね。
しかし最近では犬も人も「ほめて伸ばす育て方」ばかりが取り上げられてしまっています。ほめて伸ばす・・・。一見とても簡単そうに見えますが本当にやってみると一般の人にはなかなか難しいものなんです。子供が100人いたら100通りの子育てがあります。遺伝子だって環境だってそれぞれちがうので、一律同じようなしつけをしても全員が理解できるとは限らないのです。犬も同じです。(遺伝的に言えばもっと複雑になります)
そしてその「ほめて伸ばす」を勘違いしているオーナーさんやママがとっても増えていると感じます。
もし愛犬が他人に迷惑がかかる行動をしたときは、オーナー(親)として本気で叱らなくてはいけません。基本的なことができないのに、オスワリ、オテ、マテができればうちの犬は大丈夫!と思っている方が多いのも事実です。子供にしたら勉強できるけど、挨拶ができない、ムカつくと暴力をはたらくのと一緒です。
最近は高齢の方が犬と暮らすことが増えてきています。犬を飼う前にもう一度考えていただきたいのが、犬は孫ではなく自分の子という感覚をもってもらいたいのです。孫はどんなひどい子になっても親に責任があります。
犬はお孫さんと同じ感覚で甘やかしてしまうと良きリーダーが不在という状態になり心理的に安定しません。
それどころか人をなめてかかってくるようになります。
そうなると人は何でも言うことを聞いてくれる、暴れたり、噛んだりすれば大丈夫という自信を自然と身につけてしまうことになります。
そうならないためにも飼う前にもう一度子育てを頑張ろうという志で犬と生活をしてもらいたいです。
犬の脳みそは何歳になっても子供の3歳児と一緒です。
YES/NOが大事なのです。何歳になってもできることもほめてもらいたい、たまには失敗するけどそれもきちんと叱ること。
今日は叱らなくてもいいかな~はダメ!
その積み重ねがいいワンちゃんを作り上げていきます。
ほめて伸ばすだけじゃいい子は育ちません。
オーナー(親)として愛情を持った直観的な叱りがわんちゃんにも子供にも一番響くものだと思っています。
私はお客様のわんちゃんをトレーニングするときうちの犬以上に愛します。
この愛するというのは上辺だけで「かわいいー」と連呼するのではなく(笑)(←よくいるペットショップの店員みたいに)この子はこうゆうとこはお利口だけどここが苦手なのね、苦手な部分を克服できるようアシストしてあげましょうという感じで触れ合っていきます。
そしてオーナー家族の雰囲気に合わせたトレーニングを行います。シャキシャキした家族にはキビキビとコマンドを出したり、マイペースな家族にはできるだけテンションを上げずに。。。など意外と工夫しています(笑)
ただ、最後の仕上げはやっぱりオーナーなのです。オーナーさんが親として立ち向かうことができなければ問題行動はおさまりません。親として、我が子(犬)に対して深い愛情を持って接していかなければならないのは、子育ても犬育ても共通したことなのです。
わんちゃんのワガママを許してしまっているオーナーさん、この機会にもう1度わんちゃんとの暮らし方を考えてみてくださいね。

右側が私の小さいころです。 犬は初代シェパードの太郎くん♪
洋服が昭和で笑えます!
子供に「して良いこと・悪いこと」を教えるのは、親の役目ですよね。犬を家族にするということは、人間の子供の親になったと同じこと。社会の一員として暮らしていく上で大事なことを教え、明るい思いやりのある子にする育て方は、人間の子育てと同じなのでしょうか?違うのでしょうか?実は、共通するところがたくさんあるんですよ。
私は良くトレーニングに来られたオーナーさんに「犬は子供と一緒!」とよく言います。それは私自身が現在ママだからわかることなのかもしれません。独身の時には全く気づきもしませんでしたが、自分の子供といぬのトレーニングは似ていることが多いなぁ~と感じて犬のしつけ同様にうちの子供たちを育てました。
まず、犬も子供も≪他人に迷惑をかけない≫というのを大切にしています。犬の場合は人を噛まない、無駄吠えしない、むやみに飛びつかない、他犬に慣れる。がどんなわんちゃんでもとっても大切なこと。
人の子の場合は友達に手を出さない、挨拶をきちんとする、危ない行動をとらない、他人がいるところで騒がせない、が大切ですよね。
しかし最近では犬も人も「ほめて伸ばす育て方」ばかりが取り上げられてしまっています。ほめて伸ばす・・・。一見とても簡単そうに見えますが本当にやってみると一般の人にはなかなか難しいものなんです。子供が100人いたら100通りの子育てがあります。遺伝子だって環境だってそれぞれちがうので、一律同じようなしつけをしても全員が理解できるとは限らないのです。犬も同じです。(遺伝的に言えばもっと複雑になります)
そしてその「ほめて伸ばす」を勘違いしているオーナーさんやママがとっても増えていると感じます。
もし愛犬が他人に迷惑がかかる行動をしたときは、オーナー(親)として本気で叱らなくてはいけません。基本的なことができないのに、オスワリ、オテ、マテができればうちの犬は大丈夫!と思っている方が多いのも事実です。子供にしたら勉強できるけど、挨拶ができない、ムカつくと暴力をはたらくのと一緒です。
最近は高齢の方が犬と暮らすことが増えてきています。犬を飼う前にもう一度考えていただきたいのが、犬は孫ではなく自分の子という感覚をもってもらいたいのです。孫はどんなひどい子になっても親に責任があります。
犬はお孫さんと同じ感覚で甘やかしてしまうと良きリーダーが不在という状態になり心理的に安定しません。
それどころか人をなめてかかってくるようになります。
そうなると人は何でも言うことを聞いてくれる、暴れたり、噛んだりすれば大丈夫という自信を自然と身につけてしまうことになります。
そうならないためにも飼う前にもう一度子育てを頑張ろうという志で犬と生活をしてもらいたいです。
犬の脳みそは何歳になっても子供の3歳児と一緒です。
YES/NOが大事なのです。何歳になってもできることもほめてもらいたい、たまには失敗するけどそれもきちんと叱ること。
今日は叱らなくてもいいかな~はダメ!
その積み重ねがいいワンちゃんを作り上げていきます。
ほめて伸ばすだけじゃいい子は育ちません。
オーナー(親)として愛情を持った直観的な叱りがわんちゃんにも子供にも一番響くものだと思っています。
私はお客様のわんちゃんをトレーニングするときうちの犬以上に愛します。
この愛するというのは上辺だけで「かわいいー」と連呼するのではなく(笑)(←よくいるペットショップの店員みたいに)この子はこうゆうとこはお利口だけどここが苦手なのね、苦手な部分を克服できるようアシストしてあげましょうという感じで触れ合っていきます。
そしてオーナー家族の雰囲気に合わせたトレーニングを行います。シャキシャキした家族にはキビキビとコマンドを出したり、マイペースな家族にはできるだけテンションを上げずに。。。など意外と工夫しています(笑)
ただ、最後の仕上げはやっぱりオーナーなのです。オーナーさんが親として立ち向かうことができなければ問題行動はおさまりません。親として、我が子(犬)に対して深い愛情を持って接していかなければならないのは、子育ても犬育ても共通したことなのです。
わんちゃんのワガママを許してしまっているオーナーさん、この機会にもう1度わんちゃんとの暮らし方を考えてみてくださいね。

右側が私の小さいころです。 犬は初代シェパードの太郎くん♪
洋服が昭和で笑えます!
2009年10月19日
トレーニングはいつからするの?
トレーニングをご希望されるお客様から寄せられる質問の中に、
[トレーニングするのは一番良いときはいつなの?]といった声があります。
正直に言いますと、その犬によって、トレーニングポイントが違いますので、個体差があるとしか言えません。
ただ、ヒルズの研究報告によると、子犬の知能(脳の働き)は生後4,5ヶ月まで急激に成長し、そこから8ヶ月くらいにはゆっくり少しずつ発達していき、その後、亡くなるまで変わらないという研究報告がありました。
そうしたことから考えても、4,5ヶ月にあえてトレーニングすることは好ましくなく、その時期にはたくさんの社会性、環境に適応できる脳を基盤として作っていくことが望ましいのです。
一般の飼い主の方は、早い時期に訓練しないと・・・!と考えられているかもしれませんが、この時期にもっとも必要なトレーニングとはパピートレーニング程度で十分なのです。
もし、早い時期にオスワリ・フセ・オテなどのトレーニングをいれていくと、脳の発達が頂点に達したとき、飼い主がオスワリと言う前に座ってしまったり、勝手にオテをしたりと、こうすれば喜ぶんでしょっといわんばかりにやってしまいます。この行動をたいていの人は賢い犬だとか可愛いとかで済ませてしまっているのです。
私は、犬に自分が指示を出す前にしてしまった行動に対して絶対褒めることはありません。なぜなら、人の行動を先読みすることを教えてしまうと、犬が嫌なとき、我慢できないときに人より早く行動し、唸ったり、吠えたりといった問題行動が出やすくなってしまう恐れがあるからです。
8ヶ月くらいになると、個性が出てきて、わがままをいう子も出てきます。
特に虚勢を行っていないオス犬はこの頃、後足を少しずつ上げてオシッコをするようになります。
この時期が、第1反抗期になり、一番トレーニングするにはいい時期でしょう!
メス犬も、アマガミが直らないなどといった子でしたら、一番激しいアマガミの時期になります。
また、発情がきてちょっとイライラしたりします。
こういった時期を見逃さず、昨日とは一線をおいてトレーニングを開始すると、かなり落ち着いた犬になります。
これは脳の働きを十分に使わせたために、ストレスなく満たされた状態になるからです。
ここでのトレーニングの注意点はむやみに怒ったりせず、褒めてのばせるようにトレーニングしていくことです。
飼い主さんとトレーニングすると、楽しくて仕方がないといった犬にしていくのが大事です。
こういったことから考えてまとめてみますと、
4,5ヶ月 社会性、人なれ、パピートレーニング
8ヶ月~ アイコンタクト、フリートレーニング、基本トレーニング(オスワリ・フセ・ツケ・マテ・コイ)
そしてその後、その犬が亡くなるまで、些細なことでも褒めていく必要があります。
オスワリはできるから褒めない。ではありません。
犬の脳内年齢は人間の3歳児と同じくらいと言われています。
3歳の子が自慢げにできた!と表現してきたら褒めてあげますよね?
犬はずっと3歳児なのです。なので、当たり前にできることも褒めてあげないと、チョッとしたことで問題行動が出てきてしまいます。
特に賢い犬には心の底から褒めないとそういった感情もすべて見透かされてしまいます。
適当に褒めて通用する犬は、実は脳内年齢が低い子でもあります。
この子達はずる賢さを知らない、考えない犬たちです。ペットとしては飼いやすいのかもしれませんが、私にはちょっと物足りないかな?と言った感じです。
それとは逆に、一般的にバカ犬と呼ばれてしまう犬たちは、人間の行動を先読みしてしまうために、いうことをきかないおバカな犬と言われがちですが、実はこういう犬がトレーニングすると、ものすごくコントロールしやすい犬になるのです。
実際には犬種や遺伝などによっても、トレーニングポイントが違いますし、飼い主様がどのようなトレーニングをお望みなのかなど、ご相談の上飼われる事をお勧めいたします。
愛犬とは10数年の付き合いになりますので、安易に可愛いという考えで飼われると、飼い主も犬も苦労する結果になる場合もありますので、不安な方はお気軽にご相談ください。

[トレーニングするのは一番良いときはいつなの?]といった声があります。
正直に言いますと、その犬によって、トレーニングポイントが違いますので、個体差があるとしか言えません。
ただ、ヒルズの研究報告によると、子犬の知能(脳の働き)は生後4,5ヶ月まで急激に成長し、そこから8ヶ月くらいにはゆっくり少しずつ発達していき、その後、亡くなるまで変わらないという研究報告がありました。
そうしたことから考えても、4,5ヶ月にあえてトレーニングすることは好ましくなく、その時期にはたくさんの社会性、環境に適応できる脳を基盤として作っていくことが望ましいのです。
一般の飼い主の方は、早い時期に訓練しないと・・・!と考えられているかもしれませんが、この時期にもっとも必要なトレーニングとはパピートレーニング程度で十分なのです。
もし、早い時期にオスワリ・フセ・オテなどのトレーニングをいれていくと、脳の発達が頂点に達したとき、飼い主がオスワリと言う前に座ってしまったり、勝手にオテをしたりと、こうすれば喜ぶんでしょっといわんばかりにやってしまいます。この行動をたいていの人は賢い犬だとか可愛いとかで済ませてしまっているのです。
私は、犬に自分が指示を出す前にしてしまった行動に対して絶対褒めることはありません。なぜなら、人の行動を先読みすることを教えてしまうと、犬が嫌なとき、我慢できないときに人より早く行動し、唸ったり、吠えたりといった問題行動が出やすくなってしまう恐れがあるからです。
8ヶ月くらいになると、個性が出てきて、わがままをいう子も出てきます。
特に虚勢を行っていないオス犬はこの頃、後足を少しずつ上げてオシッコをするようになります。
この時期が、第1反抗期になり、一番トレーニングするにはいい時期でしょう!
メス犬も、アマガミが直らないなどといった子でしたら、一番激しいアマガミの時期になります。
また、発情がきてちょっとイライラしたりします。
こういった時期を見逃さず、昨日とは一線をおいてトレーニングを開始すると、かなり落ち着いた犬になります。
これは脳の働きを十分に使わせたために、ストレスなく満たされた状態になるからです。
ここでのトレーニングの注意点はむやみに怒ったりせず、褒めてのばせるようにトレーニングしていくことです。
飼い主さんとトレーニングすると、楽しくて仕方がないといった犬にしていくのが大事です。
こういったことから考えてまとめてみますと、
4,5ヶ月 社会性、人なれ、パピートレーニング
8ヶ月~ アイコンタクト、フリートレーニング、基本トレーニング(オスワリ・フセ・ツケ・マテ・コイ)
そしてその後、その犬が亡くなるまで、些細なことでも褒めていく必要があります。
オスワリはできるから褒めない。ではありません。
犬の脳内年齢は人間の3歳児と同じくらいと言われています。
3歳の子が自慢げにできた!と表現してきたら褒めてあげますよね?
犬はずっと3歳児なのです。なので、当たり前にできることも褒めてあげないと、チョッとしたことで問題行動が出てきてしまいます。
特に賢い犬には心の底から褒めないとそういった感情もすべて見透かされてしまいます。
適当に褒めて通用する犬は、実は脳内年齢が低い子でもあります。
この子達はずる賢さを知らない、考えない犬たちです。ペットとしては飼いやすいのかもしれませんが、私にはちょっと物足りないかな?と言った感じです。
それとは逆に、一般的にバカ犬と呼ばれてしまう犬たちは、人間の行動を先読みしてしまうために、いうことをきかないおバカな犬と言われがちですが、実はこういう犬がトレーニングすると、ものすごくコントロールしやすい犬になるのです。
実際には犬種や遺伝などによっても、トレーニングポイントが違いますし、飼い主様がどのようなトレーニングをお望みなのかなど、ご相談の上飼われる事をお勧めいたします。
愛犬とは10数年の付き合いになりますので、安易に可愛いという考えで飼われると、飼い主も犬も苦労する結果になる場合もありますので、不安な方はお気軽にご相談ください。
タグ :しつけ
2009年06月07日
抱っこ禁止令??
小型犬を飼っていらっしゃる方の中に、気づかない間に抱っこ癖がついていませんか?
お散歩中に他の犬に吠えたから抱っこ。
知らない場所で興奮したから抱っこ。
おうちで来客中にうるさいから抱っこ。
抱っことせがんでくるので、しかたないので抱っこ。
抱っこすると一見落ち着いたかのように見えますが、これは大きな勘違いです。
問題行動をなくしてるのではなく、回避しているだけです。また、より頭のいい犬は、自分の要求を満たしてくれたとご満悦になってしまい、更なる問題行動を膨らめる原因にもなります。
特に多いのが、抱っこ中に他人が手を出すと噛んだり、唸ったりする犬です。
これは長年積み重ねてしまった、行為が犬をエスカレートさせてしまった結果です。
抱っこ好きの多くの犬には、自分のことを犬だと理解していない犬が多くいます。
まずは、犬は犬目線で社会性を学ばせることが大切です。
興奮したり、知らない犬が散歩中にすれ違うときなどは、頑張ってオスワリ・マテをさせるようにしましょう。
お家に来客があるときなどは、積極的に協力していただいて、おやつをもらうなどして、お客さんはいい人という印象をつけましょう。そして、チャイムが鳴ったらハウスに入るとおやつがもらえるというゲームを犬に教えてしまいます。始めのうちは根気がいりますが、頑張って何度も挑戦していくと犬は遊び感覚でスグ覚えてしまうでしょう。
抱っことせがむ犬は、大型犬だと思うようにして、その要求には答えません。逆に犬が抱っこを望んでいないときに抱っこするのが理想的です。
実際にやってみるとなかなか、思うように行かないことの方が多いかも知れませんが、少なくとも抱っこをスグしていたときよりは、少しずつかもしれませんが愛犬に変化が現れるでしょう。
小さくて、何かあったらどうしよう?という不安が犬には一番よくないことです。
飼い主は常に毅然とした態度で犬をコントロールする必要があるのです。
お散歩中に他の犬に吠えたから抱っこ。
知らない場所で興奮したから抱っこ。
おうちで来客中にうるさいから抱っこ。
抱っことせがんでくるので、しかたないので抱っこ。
抱っこすると一見落ち着いたかのように見えますが、これは大きな勘違いです。
問題行動をなくしてるのではなく、回避しているだけです。また、より頭のいい犬は、自分の要求を満たしてくれたとご満悦になってしまい、更なる問題行動を膨らめる原因にもなります。
特に多いのが、抱っこ中に他人が手を出すと噛んだり、唸ったりする犬です。
これは長年積み重ねてしまった、行為が犬をエスカレートさせてしまった結果です。
抱っこ好きの多くの犬には、自分のことを犬だと理解していない犬が多くいます。
まずは、犬は犬目線で社会性を学ばせることが大切です。
興奮したり、知らない犬が散歩中にすれ違うときなどは、頑張ってオスワリ・マテをさせるようにしましょう。
お家に来客があるときなどは、積極的に協力していただいて、おやつをもらうなどして、お客さんはいい人という印象をつけましょう。そして、チャイムが鳴ったらハウスに入るとおやつがもらえるというゲームを犬に教えてしまいます。始めのうちは根気がいりますが、頑張って何度も挑戦していくと犬は遊び感覚でスグ覚えてしまうでしょう。
抱っことせがむ犬は、大型犬だと思うようにして、その要求には答えません。逆に犬が抱っこを望んでいないときに抱っこするのが理想的です。
実際にやってみるとなかなか、思うように行かないことの方が多いかも知れませんが、少なくとも抱っこをスグしていたときよりは、少しずつかもしれませんが愛犬に変化が現れるでしょう。
小さくて、何かあったらどうしよう?という不安が犬には一番よくないことです。
飼い主は常に毅然とした態度で犬をコントロールする必要があるのです。
タグ :無駄吠え
2009年04月23日
虚勢手術はしたほうがいいの?
オス犬を飼った場合、みなさん、獣医さんやペットショップで虚勢を進められませんでしたか?
ここでは、しつけの面から虚勢について考えていきたいと思います。
まず、考えていただきたいのが、今後繁殖をするつもりがあるのかどうかです。そしてそのお相手がいるかどうかです。ただ、手術するのはかわいそうと思うだけなら、もう1度考えてみてください。
これは私の経験から言っていることです。違っていましたらご了承ください。
オス犬は生まれてから、5ヶ月から9ヶ月ごろにオシッコのとき片足をあげてするようになります。
少しづつ足が高くあっがってきた頃、オス犬の第1反抗期が始まってきます。
今まで、いい子だったのが突然うなったり、言う事をきかなくなったり、わがままになります。
この頃の犬は、飼い主がどこまで自分のわがままを許すのか伺っていることが多いのです。
たいていの飼い主さんは、今日はイライラしてるだけなんだと、気づきません。
これをそのままにしておくと、1歳半~2歳半頃に第2反抗期がきます。第2期では今までのような叱り方では、犬になめられてしまっているため、まったくきかず、とにかくわがままを貫き通そうとします。
これじゃまずいと、焦って、変な叱り方をしてしまうと、噛み付いたり、時には触れなくなる犬も出てきます。
第1期も第2期も、ある日突然やってきます。これをこのまま見過ごして生活していると、何かしらの問題行動が勃発し、訓練所へ・・・ということになるのです。
これは、飼い主の責任でもありますので、心構えをしておきましょう!
では、反抗期をなくすためにはどうしたらよいのでしょう?
まずは、パピートレーニングを週に1回は行ってください。(3ヶ月~2歳ごろまで)
そして、子犬の足がオシッコをするときに上がり始めたくらいに、虚勢手術をします。
手術をしても、気が強い犬は中にはいますが、手術してみないとこれは分かりません。
手術することによって性欲がなくなり、エサ欲が強くなるため、しつけなどコントロールが楽になります。
また、トイレのときもカケションをしない犬になりますので、トイレシーツにきちんと失敗なくできるため、褒める回数も増えるので、コミュニケーションが自然にとれていきます。
もう、1歳半をすぎて足が上がってしまった犬でも、性欲がなくなるため、ストレスの軽減になります。
性欲は本能です。室内で飼っていても、お散歩のときに、メス犬の臭いはすぐかぎ分け、ムラムラした状態で家に帰り、モンモンとした気持ちで飼い主と生活していて、気に入らないことがあり噛んでしまう、というケースは多いのです。そこから噛む癖が始まってしまったという犬も多いのです。
去勢をしていない犬が、いつもと様子がおかしかったりするときは、近所の女の子が発情だったりします。たいてい、春と秋が多いので、その頃は注意が必要です。(トイレの失敗などもあります)
もし、これから、犬を飼おうとお考えなら、虚勢をするかしないかはご家族で真剣にお考えください。
特に、毎日世話をされる方の考えを重視されると良いでしょう。
ここでは、大雑把にお伝えしていますので、去勢をしなくても、いい子はたくさんいます。
不安な方は、ご購入の際にお問い合わせください。
ここでは、しつけの面から虚勢について考えていきたいと思います。
まず、考えていただきたいのが、今後繁殖をするつもりがあるのかどうかです。そしてそのお相手がいるかどうかです。ただ、手術するのはかわいそうと思うだけなら、もう1度考えてみてください。
これは私の経験から言っていることです。違っていましたらご了承ください。
オス犬は生まれてから、5ヶ月から9ヶ月ごろにオシッコのとき片足をあげてするようになります。
少しづつ足が高くあっがってきた頃、オス犬の第1反抗期が始まってきます。
今まで、いい子だったのが突然うなったり、言う事をきかなくなったり、わがままになります。
この頃の犬は、飼い主がどこまで自分のわがままを許すのか伺っていることが多いのです。
たいていの飼い主さんは、今日はイライラしてるだけなんだと、気づきません。
これをそのままにしておくと、1歳半~2歳半頃に第2反抗期がきます。第2期では今までのような叱り方では、犬になめられてしまっているため、まったくきかず、とにかくわがままを貫き通そうとします。
これじゃまずいと、焦って、変な叱り方をしてしまうと、噛み付いたり、時には触れなくなる犬も出てきます。
第1期も第2期も、ある日突然やってきます。これをこのまま見過ごして生活していると、何かしらの問題行動が勃発し、訓練所へ・・・ということになるのです。
これは、飼い主の責任でもありますので、心構えをしておきましょう!
では、反抗期をなくすためにはどうしたらよいのでしょう?
まずは、パピートレーニングを週に1回は行ってください。(3ヶ月~2歳ごろまで)
そして、子犬の足がオシッコをするときに上がり始めたくらいに、虚勢手術をします。
手術をしても、気が強い犬は中にはいますが、手術してみないとこれは分かりません。
手術することによって性欲がなくなり、エサ欲が強くなるため、しつけなどコントロールが楽になります。
また、トイレのときもカケションをしない犬になりますので、トイレシーツにきちんと失敗なくできるため、褒める回数も増えるので、コミュニケーションが自然にとれていきます。
もう、1歳半をすぎて足が上がってしまった犬でも、性欲がなくなるため、ストレスの軽減になります。
性欲は本能です。室内で飼っていても、お散歩のときに、メス犬の臭いはすぐかぎ分け、ムラムラした状態で家に帰り、モンモンとした気持ちで飼い主と生活していて、気に入らないことがあり噛んでしまう、というケースは多いのです。そこから噛む癖が始まってしまったという犬も多いのです。
去勢をしていない犬が、いつもと様子がおかしかったりするときは、近所の女の子が発情だったりします。たいてい、春と秋が多いので、その頃は注意が必要です。(トイレの失敗などもあります)
もし、これから、犬を飼おうとお考えなら、虚勢をするかしないかはご家族で真剣にお考えください。
特に、毎日世話をされる方の考えを重視されると良いでしょう。
ここでは、大雑把にお伝えしていますので、去勢をしなくても、いい子はたくさんいます。
不安な方は、ご購入の際にお問い合わせください。
タグ :虚勢・避妊
最近の記事
【アニコム】個人情報保護に関する基本方針 (5/11)
アニコム保険 勧誘方針について (8/25)
第6回 スキッパ会開催いたしました★ (7/7)
第6回 スキッパ会開催します★ (3/26)
犬の育て方は子育てとほぼ一緒★ (10/5)
第5回 スキッパ会 開催いたしました★ (6/13)
第5回 スキッパ会 参加者のご確認のお願い☆ (5/12)
弟5回 スキッパ会 開催決定のお知らせ★ (2/17)
トリマーとトレーナー募集中です★ (7/9)
過去記事
お役立ち情報QRコード

最近のコメント
macmillan / 犬の体温を知っておこう!